ディシプリン(学問領域)に
とらわれない思考を身につけたい
第1回 03月03日 伊達 聖伸
フランスとケベックにおけるイスラームのヴェール問題
今年は、フランスの公立校で生徒によるイスラームのヴェールの着用が禁止されてから20年、ケベックの学校で教員によるヴェールの着用が禁止されてから5年になります。なぜ、西洋の一部の国や社会ではイスラームのヴェール着用が問題になるのでしょうか。この回では、その歴史的・社会的背景を押さえ、視線の文化の観点から、またヴェールを着用する当事者の戦略を、「装う」という観点から、ヴェール問題にアプローチします。
- 講師紹介
-
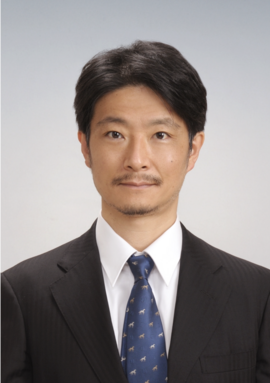
- 伊達 聖伸
- 東京大学大学院総合文化研究科地域研究専攻フランス小地域教授。専門は宗教学・フランス語圏のライシテ(世俗主義、政教分離)。おもな著作に、『もうひとつのライシテ――ケベックにおける間文化主義と宗教的なものの行方』(岩波書店、2024年)、『ライシテから読む現代フランス――政治と宗教のいま』(岩波新書、2018年)など、本講義と関係の深い訳書として、フランソワ・オスト『ヴェールを被ったアンティゴネー』(小鳥遊書房、2019年)など。
- 授業風景
2024年度の南京集中講義が幕を開けた。
今年で20回目の節目を迎えた南京での集中講義では7人の講師が3週間にわたって南京大学仙林キャンパスを舞台に「装う」のテーマのもと、授業を展開していく。
講義に先立ち開講式が行われ、南京大学の外国語学院 副院長 張俊翔先生、国際処 副処長 曹毅先生、本科生院院長 王駿先生、東京大学の伊藤徳也先生からお言葉をいただいたのち、今年度の第一講、伊達聖伸先生による『フランスとケベックにおけるイスラームのヴェール問題』が始まる。
伊達先生は東京大学大学院総合文化研究科所属で宗教学、特にフランス語圏におけるライシテを研究されている方である。
フランスにおけるライシテはしばしば政教分離と表現されるフランスの制度であるが、先生によるとライシテには2つの側面があるという。1つ目は教権主義的なカトリックに代表される原理主義的な宗教と戦うという面、2つ目はさまざまな宗教の自由を認めて共生の社会を実現しようとする側面である。そんなライシテについて、フランスとケベックのイスラームのヴェール問題に焦点を当てて考察していこう、というのが本講義の主眼である。
教室には伊達先生の日本語の声が響き渡る。生徒たちは各々のイヤフォンやヘッドフォンを装着し、耳元からは南京大学の日本学科の修士学生である肖慧文さんと唐懿昕さんによる淀みのない同時通訳が届けられる。生徒の手元に目を向けると、通訳の両氏が事前に準備した中国語の講義資料が広げられ、授業が進むにつれ少しずつ書き込みが増えていった。
最初に先生が問いかける。ライシテという言葉を聞いたことがある人は手をあげてください、と。
同時通訳の時差があれどなかなか生徒の手はあがらない。生徒にとっては、ライシテというこれまで馴染みのない言葉に若干の緊張が走る。先生はゆっくりと、丁寧に、授業の導入を始める。
昨年行われたパリ五輪の開会式での2つのシーンを話題に上げる。
1つはマリー・アントワネットを模した人物が自らの首を手に歌うシーン。もう1つは、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画『最後の晩餐』を模した10人のドラァグクイーンが登場するシーンである。いずれのシーンも日本国内において大きな反響を呼んだシーンであり、賛否両論を呼ぶものであった。これらの賛否の焦点は「装い」に向けられ、主に宗教(キリスト教)的な批判を生むものとなり、各々の立場により賛否が分かれるものとなっていた。
かのローマ教皇は遺憾の意を表明し、現米国大統領ドナルド・トランプ氏が「恥晒し」と揶揄したこの演出が大きな議論を生んだことは記憶に新しい。
また、この2024年パリ五輪において話題になったことがもう1つある。フランスの陸上選手が頭にイスラームのヴェールを被ることができるかという論点である。
フランスにおいてライシテと「装い」の規制は関わりが複雑で難しいものである。
2023年秋にはムスリムが着る長い服であるアバヤの着用が公立校で禁止された。しかしここにも当事者間でいくばくかの認識の相違が生じている。伊達先生によれば、規制する側であるフランスの政府視点から見ればアバヤには宗教的意味がはらんでいるという解釈となるが、本来のアバヤというものはムスリム的な視点に立つとただの長い服を着る、という習慣や流行といったものであり、そこに宗教的な意味合いは持っていない。あくまでもフランス政府側がアバヤという衣装に対して一方的に宗教的意義を見出しているのに過ぎないのである。他にも2024年の秋にはフランス、リールのトゥルコアンの公立校にてとある生徒が下校時に校門を通り過ぎる前に学校敷地内でヴェールを被ったことにより言い争いになり、このニュースはフランス国内で大きな議論を呼ぶこととなった。
イスラームのヴェール問題をめぐってはフランス国内でも数多くの議論を巻き起こすものとなっている。このような議論は、しばしばフランスの厳格な政教分離や宗教風刺に対するイスラームの原理主義や「ヴェールの少女」の対立構造として捉えられる。
昨今のフランス情勢を鑑みると確かにそういった対立構造としてこの問題を捉えたくなるものである。イスラームの過激派による襲撃は数知れず、2015年11月、パリで発生した同時多発テロはセンセーショナルなものであった。他にも2020年10月にはフランス国内で教師がチェチェン出身の過激派に斬首される事件も発生している。ことの発端はムハンマドの風刺画を授業内で見せたことだと言われている。それのみにとどまらずパリの郊外で学校の先生が殺されるような事件が発生している。つまり、フランス国内においては厳格な政教分離への対立的なものとしてイスラームの原理主義というものが存在し、そのアイコン的なものとして「ヴェールの少女」というものが存在している、という図式や表象で理解されがちなのである。
伊達先生は問いかける。
確かに今は政教分離や宗教風刺とイスラームの原理主義や「ヴェールの少女」が対立しているように見える。確かにそう”見える”のである。
ただ、あくまでもそう見えるだけではないか?本当にこれらは対立しているのであろうか?
今のフランスはライシテといわれる激しい宗教批判が進んでいるように見える。
確かにそう見えるが本当にその解釈でいいのだろうか?
本講義ではこれらの問いを出発点に、イスラームの「ヴェール」問題をテーマに、考察していくものである。ヴェールは主にイスラームの女性が主に頭髪を隠すためのものである。しかし、この「ヴェール」にはそれだけにとどまらず社会的な意味を持つのではないか。「ヴェール」が隠しているものは一体何なのか?伊達先生は問いかける。
これらの問いを考察すべく、まず先生はフランスとケベックでそれぞれどのようにヴェール問題が発展してきたかをお話しされた。
まずパリのヴェール問題について。発端は1989年パリ郊外のクレイユで起きた事件にある。学校でムスリムの生徒がスカーフ(ヴェール)を纏い、教師から外すように指導されたものを拒否したところ生徒が退学処分となったという事件である。この事件はフランスの社会を2分する大激論を引き起こし、ついにはフランス国民教育大臣が国務院にその見解を求めるに至った。国務院の回答は生徒には学校内においても表現の自由があるとし、スカーフの着用自体がライシテの原則に反するものではない、という見解であった。しかし、1994年にもヴェール問題は再燃し、度々議論を巻き起こしていた。ついには、2004年、フランス国内の公立校でヴェール禁止法が発令されることとなる。2004年ヴェール禁止法の背景にはいくばくかの考慮すべき背景が存在している。フランス社会でのライシテを維持する上でイスラーム原理主義への警戒的な文脈からこの動きは始まったものである。
さらに規制は強化され、2010年には公共空間でのブルカ着用を禁止する法律も成立した。2023年にはアバヤ・カミスも法律で禁止となり、その制限は厳しさを増している。
続いてカナダ、ケベックのヴェール問題について。 ケベックは歴史を辿るとフランスからカトリックの宣教師が来て発展してきた地域である。特筆すべきはフランスは共和国であったのに対し、ケベックは革命を経験しておらず、独自の発展を遂げてきた。そんなケベックでヴェール問題がどのように発展してきたかみていこう。
1960年代の「静かな革命」を経てもライシテという考えがそこまで浸透しなかったケベックにおいて、ヴェール問題がはじめて表層化したのは1994年のことである。時を同じくしてフランスで起きていたヴェール論争が飛び火する形でケベックでも議論が巻き起こることとなった。その際、ケベックの人権委員会はヴェール着用は「生徒に当然に認められる権利」という結論を出して、公立校でのヴェール着用について、現在に至るまで権利が保障され続けている。 2006年から2007年にかけては「妥当な調整」論争と呼ばれる議論が激化した。
発端となった事件は学校であるシク教徒の生徒が儀礼用の短剣を落とした、というものであった。当然、儀礼用のものだが使い方によっては凶器になるという理由で学校側は短剣の持ち込みを禁じた。このことの是非について、裁判が行われ、1審2審は学校側の判断を支持したものの3審では原告側の訴えを認め、学校側の判断を不適切としたものである。 この判決は大きな論争を呼び起こすこととなる。「移民のいうことはよく聞く」と指摘され、マジョリティ側が声を上げたのである。この際、ヴェール問題も同じくこの論争の焦点となった。たとえば、あるサッカーの大会にて、ある女子選手がヴェールをかぶって試合に出たところ、審判に出場を止められた。前の試合ではかぶっても問題なかったとのことで、ケベックのFA(サッカー協会)とカナダのFAで意見が分かれるほどの論争となった。他にも、顔を覆うような服装で投票所に来た場合には投票を認めるのかという論争について一部のメディアがブルカをかぶっていても投票を認めるとリークしたことによりケベック社会で反対運動が起きることとなる。 これらの諸問題はブシャール=テイラー委員会において以下のようなフランス本土と明らかな違いを意識した考えを打ち出し、問題は収束へむかうこととなったという。この考え方はケベックはライシテの社会ではあるが「開かれたライシテ」の社会であるという考え方である。すなわち、信教の自由は守るべきだという論調のものであり、生徒のヴェール着用を制限することはできないという立場のものである。
その後、ヴェール問題の転機となったのは2013年のケベック価値憲章にかかわる議論である。この憲章により公務員には認められないような服装を規定するという法案が出されたことにより議論が発展することになる。このような考え方はフランスと似通ったものであり、最終的に法案は採択されなかったものの大きな転換点となった。この後も、顔を見せないヴェールは問題として終わらず、例えば語学の授業のとき、ニカブ(顔を覆うような衣装)は顔が見えないから規制したほうがいいのではないかといった議論が巻き起こることとなる。
その結果、2017年にはヴェール禁止法としてヴェールの着用を禁止する法律が北米で初めて制定されることとなった。これは要するに、公共サービスを行う/受ける際はお互いに顔を見せましょう、という趣旨の法律である。しかしながら極寒のケベックにあり、冬にはムスリムでなくとも顔を覆うものである。それでは、公共のバスに乗る時はどうするのか、乗車中もずっと顔を見せているのだろうか。結局、この法律は実際には適用することができないものであったのである。
そして、2019年には教員がヴェールを被ることを禁止とする法律ができることとなる。フランス本土と比べると、生徒に対する規制はないことに特徴があるといえよう。
伊達先生はこれまでのフランスとケベックにおけるヴェール問題の動向を紹介した上で両者の違いについて説明をはじめる。
まず、そもそもライシテとは何か。 伊達先生は1905年、フランスで定められた政教分離法を詳しく解説し始めた。第一条で「共和国は良心の自由を保障する。共和国は宗教の自由を保障する」という旨を謳った上で、第二条で政教分離を謳っている、これが政教分離法である。すなわち、この法律は条文内でもヴェール問題について葛藤を起こしうるものなのである。ライシテが信教の自由を保障するのであればライシテはヴェールを認めないといけない。ただ、国家と宗教、共和国と宗教の政教分離を考えればスカーフは認められないということである。この解釈は、1989年当時のフランスのミッテラン政権ではヴェール問題の結論を国務院に判断を仰いだ結果、スカーフの着用自体はライシテの考えと矛盾しないものの、宗教を理由に授業のボイコットや布教や改宗を促すことはは認められない、という基準に落ち着くこととなった。
しかし15年後の2004年、フランスでは法律でヴェール着用が禁止されたのである。右派のシラク大統領が学識者を集めて会議を行なったスタジ委員会の提言を受けてヴェール着用は法律で規制されることとなる。その背景には2001.09.11の同時多発テロでの西洋社会からのイスラームのイメージが悪化したことがあるのだが、一度は認められたヴェール着用をなぜ禁止することができたのか。そのロジックがどういったものだったのか。
先生によると、ここでもやはりライシテの理念の解釈のものになるのである。ライシテは政教分離をすることによって信教の自由を確保するものであると考える。このとき、ムスリムの未成年の女性は自分の意思でヴェールを被っているというよりも家庭などの周囲の影響から、被らされているのではないかと解釈されたのである。その当時、メディアではヴェールを被らされている話が頻出したことも影響し、ヴェールを被らされている子を救うことが人権保障の観念にも適うことになり、公立校でのヴェール着用は禁止されることとなる。この際、注意が必要なのは、自分の意思で被っているという話はほとんど出てこなかったことであると伊達先生は補足をしている。
その後、2010年に公共空間でブルカの着用が禁止されたことの捉え方についても注意が必要であると先生は指摘している。
2004年の法律に関してはライシテの法律であったヴェール禁止法だが、2010年のブルカ禁止については全く違う論理で法律が作られている。すなわちこの法律はライシテの法律ではない、ということである。ライシテの理念に照らし合わせると公共空間においてヴェールを纏うこと自体は理念に反するものではない。それでもなお、ブルカ法案は可決されたのである。そこには治安維持的な文脈が多分に含まれている。要するに顔を隠す装いであるブルカを纏う人間は危険である、というメッセージをこの法律に読み込むことが可能なので。
その後も2016年にはブルキニ論争という騒動が発生し、革命記念日にニースでトラックが暴走する事件があったことを発端に顔を覆うわけでもないブルキニが南フランスの一部で禁止される条例が制定された。最終的にはこの条例は国務院の判断によって無効とされるわけだがやはり、フランスの社会においてイスラームの装いに対しては度々議論が発生している。
2023年にはアバヤ・カミスといわれるイスラームの衣装が禁止されることとなった。アバヤは女性用、カミスは男性用のものであるが、とりわけこの際もアバヤの禁止の方に社会的な大きな注目が集まった。それまでのヴェール論争の経緯などを鑑みても、こういったヴェール問題において男性用のものよりも女性用の衣装の方が注目の対象となることが多いと伊達先生は指摘している。
ここで1日目の講義は終了し、残りの時間は質問に当てられた。 質問ではフランス社会と宗教の関わりに関するものやイスラーム以外の服装に対する規制、オリンピックやスポーツと政治宗教の関わりについてなど多岐にわたるものであった。
講義終了後にも数名の生徒が生徒が教壇のもとに訪れ、活発な議論が起きていた。中には日本語で質問する生徒もいた。
2日目
授業は前日、学生たちが記入したリアクションペーパーに対するコメントから始まる。これらは南京大学日本語学科の両氏が抜粋し、中国語で書かれたものを翻訳した上で授業当日の午前には先生のもとへと届けられていたものである。
先生はいくつか抜粋して紹介していく。一つ目は日本にいるムスリムの動向や日本社会の受け入れに対する対応に関するもの。他にも中国での法律の例を持ち出した上で、フランスではどうして教職員(公務員)ではなく学生に対して規制を課すのかといったコメントが読み上げられた。
コメントの中では日本の状況を紹介する中で日中のモスクに着目して説明されている姿が印象的であった。先生が南京滞在期間中に実際に訪れた南京の清真寺(モスク)と日本の代々木のモスクを紹介されていた。
授業に入っていく。
2日目の大きなテーマはヴェールとイスラームはどのように結びついていったのか、といったものになる。
そもそもヴェールといった衣装は本来、イスラームの特有のものではない。キリスト教の修道女たちもヴェールを纏っているのである。
先生曰く、あくまでもヴェールは歴史の過程の中で結果的にイスラームのものと認知されるようになったものであると。
先生は一枚の写真を提示した。そこには屋内でイスラーム風の衣装を纏った男性と女性が写っており、女性は黒いヴェールで顔を覆うようなものであった。
先生曰く、この写真には違和感があるという。どういった部分に感じるか学生に問いかける。男性が女性をリードしているみたい、表情がない、男性はとてもリラックスしているけど女性は緊張感を持っている、などの意見が出た。この写真のような状況は本来起こり得ないため違和感があるのだという。どういうことか。先生が指摘するポイントはどうして女性がヴェールを被るのかという部分である。イスラームでは女性の肌や顔を知らない男性に見せないようにするため、写真のような屋内かつ親密そうな男性と二人だけなら女性はヴェールを被らなくていいはずなのである。
そもそもどうしてヴェールを被るのかということを考えよう。先生はここでキリスト教とイスラームの聖典でそれぞれヴェールについてどのように書かれているのか着目してお話された。
キリスト教では新約聖書の『コリント信徒への手紙』では「女はだれでも祈ったり、預言したりする際に、頭に物をかぶらないなら、その頭を侮辱することになります。」と語られる一方、イスラームの聖典であるクルアーンでは「慎み深く目を下げて、陰部は 大事に守っておき、外部に出ている部分はしかたないが、そのほかの美しいところは人に見せぬよう。胸には蔽いをかぶせるよう。」や、「(人前に出るときは)必ず⻑衣で(頭から足まで)すっぽり体を包み込んで行くよう申しつけよ。こうすれば、誰だかすぐわかって、しかも害されずにすむ。」との旨が書かれている。
ここからわかる通り、クルアーンでは美しいものを隠せとは言っているものの、髪を隠すヴェールを纏うことを命じるような文言は書かれていない。そして、ヴェールに宗教的な意味は付加されていないのである。一方で、新約聖書では祈る時に女性は被り物をしないのであれば神を侮辱することにつながるのである、すなわちキリスト教はヴェールに対して宗教的な意味合いを見出しているといえよう。ヴェールはイスラームの宗教性と結びつけられがちであるが、むしろ宗教的な意味合いはキリスト教のほうにあると先生は指摘する。またキリスト教が祈りのときにヴェールを被るのに対して、あくまでイスラームにおいては女性が日常的にヴェールを纏うのである。これはイスラームにおいて女性がヴェールを纏うのは身の安全を守るため、という理由にも起因する。
また、先生は植民地の風俗を表す2枚の絵葉書を例に出し、お話を進められた。一つはヴェールを纏った女性のもので、もう一つは布を纏っていないものである。ただ、先生はこの両者の写真には共通点があると指摘する。それは男性の視線から捉えられたものであり、植民地主義というコンテクストの中で権威主義的な形式の中で捉えられたものであるという。すなわち2枚の写真はある意味同じであり、支配の対象になっているとのことだ。
ブルキニ論争についても先生はここで改めて触れた。当時のフランスの首相が「マリアンヌは胸をはだけている。(ヴェールを覆っていない)彼女はなぜなら自由だから」と語ったように、女性にとっての自由というのは肌を露出することであるとされているのである。ブルキニ論争の際話題になったブルキニとビキニを並べた写真は、肌の露出度合いの点から言えば対照的だが、女性の身体に対する他者からの眼差しを意識した衣服であるという意味では共通しているのである。
それではヴェールをどうして被るのかという話について。
ヴェールは危険なのか。フランスがアルジェリアを植民地化した際、アルジェリア兵がゲリラ活動をしている写真を先生は提示した。
そこにはヴェールで全身を覆った数人の人物がフランス兵とすれ違う様子が写っていた。ヴェールの中にはゲリラ兵が入っており、この後フランス兵は襲撃されたという。ここには潜在的に「ヴェールを被った人は女性」という共通認識があったがゆえにフランス兵は警戒しなかったのである。ヴェールの中には何が入っているかわからないから危険な存在に見える事情の一端が、これでわかるのではないだろうか。
1958年の「最初のヴェール事件」に触れる。1989年のヴェール事件からおよそ30年前に起きたこの事件ではフランスの女性が植民地の女性のヴェールを剥がそうとしている。すなわち、この事件がイスラーム社会の慣例から女性を解放しようとしているという風に捉えられるのではないか。チュニジアでもライシテを促進したブルギバ大統領によって「ヴェールをはがすキャンペーン」が行われたほどである。
ここで伊達先生は通りでヴェールを被った女性の写真を2枚提示した。生徒たちに問いかけながら違いを説明していく。左の写真は古典的なヴェールを被った女性の写真である。ヴェールというのは本来、隠すためのもので写真としても左の写真は隠すためにヴェールを着用している。そのため、基本的には屋外で着るものであり、知らない人にあってもヴェールを纏っていれば見られていないことにできるというわけである。一方で右の写真の女性はイキイキしている様子である。ある意味で左の写真は隠すこと、それに対して右側の写真は「隠すことを見せている」というわけである。
このような歴史的社会的背景を背負う今日の西洋のムスリム女性にとって、ヴェールを被るのか被らないのかについては、ムスリム女性たちの戦略があるという。さまざまな権力や文化のもとにヴェールを纏う戦略をとっているといえる。
あるムスリム女性は「スカーフはムスリムと非ムスリムのあいだに分断ではなく絆をもたらす」と語る。現代ではフランス社会においてヴェールを被るとフランス社会とムスリム社会に壁を作っていると思われるがそうではなく、ムスリムであるためヴェールを被っている時が自分自身であるといえることであり、本当のコミュニケーションを生む上で本当の自分を知ってもらうことでより親密な関係性を築くことができるとしている。また、この女性は他にも「スカーフは女性ではなく男性に強いられたもの」とも述べており、あくまでスカーフはイスラームが生まれた当初は身を守るために作られたものであり、西洋人の普通の人は男性によって女性に強いられたものであると指摘している。すなわち、これらは元来、女性の権利を認めるためにあったものである。他にも現代ではイスラーム社会では相続権が男性よりも少ないという問題があるが大元を辿ると当時にとっては相続権が女性には全く認められていなかった社会であった中で認めたという意味では捉え方が変わってくるであろう。彼女はイスラームに即したフランス社会にも適合できるフランス社会のあり方を補足しているのである。「イスラームの女性はこう、西洋の女性はこうとスティグマ化するのはやめよう」と。
また他の女性の声についても先生は紹介された。ケベックのムスリム女性の引用である。
彼女はヴェール着用を義務だと思ってるけど被っていない。どうしてか? 「私たちの宗教では誰もヴェールの着用を強制されない。ヴェールの着用を優先するかしないかは、結局のところ本人次第」だと語る。イスラームは非常に平等な宗教と言われている。キリスト教はヒエラルキー的で神父の言うことを聞くことになるがイスラームにとってはイマームとの関係はフラットに近い。そのため、あくまでもイスラームは神と自身の関係構造しかないため、自身がヴェールを纏うことを周囲の人物から強制されることはないというわけである。
他の女性は「被ろうと思っているけど準備ができていない。他のことができなくなる。プールにも行けなくなるし男性との関係も考えないといけない」と語る。イスラームにおいてはヴェールを被る必要があるのはわかっているが、ヴェールを被ると、他の日常生活にも関係するようになってくるというわけである。ヴェールを被るということは自制を要求されるようになるということである。ヴェールを被っているのに水着を着て泳ぐというのは不自然で、そういった事情を鑑みて準備ができたらやろうと思っているが”先延ばし”にしているという意見もある。
こういった声を紹介する経緯について、事件は取り上げるけどあまりこう言った声は聞こえてこないため、研究やインタビューを行う意義が説明されていた。
他にも、「ヴェールを被った女の子がぴっちりした服を見るのは辻褄が合わず、ヴェールを身につけるということはけじめをつけるということ」だと指摘する声がある。また、あるケベックのムスリム女性は「アラブの国々では非ジャブをかぶっていながら体のラインが見える服を着て厚化粧をしている女の人が大勢いる。ああいう国ではヴェールの深い意味は失われてしまったと思う。あっちではただの慣習のようなもの。もはや宗教的なものではない。だからこそ強制的に被らされているのでしょう。よくわからないけれどヒジャブをかぶるよう強制するのは良くないと思う。こっち(ケベック)には自由がある。私たちの宗教選びにとってよりよく知ることができる」と発言している。アラブ諸国では完全に慣習化してしまった一方で西洋社会ではマイノリティであるものの宗教の自由が保障されていることから、自身の信念に基づいてヴェール着用の判断をしているため、より深い理解をできると指摘している。ヴェールを被っていない黒人のムスリムは周囲の人が「(ムスリムだと思っていないため、)ヴェールを被っているため就職の面接できても採用しないよね」といっていたと語る。
これらのように、歴史的社会的背景を背負ったフランス、ケベックの社会の中にスカーフというものがあってそれを「装う」ということにはさまざまな戦略がある。ヴェールを被る、あるいは被らないというところにもさまざまな判断がはたいらいており、社会の中の権力関係の中でそれぞれが自分自身を位置付ける戦略を行使する様が浮かび上がってくると先生は指摘している。
講義はここで終わり、最後は30分ほど質疑応答の時間が取られた。以下に質問のおおよその内容について一問一答的に記録していく。
Q(学生)「中国の100年前、中華民国が成立した時、清王朝で辮髪を切る運動があった。当時は辮髪を切ることを嫌がる運動がありました。ここにヴェール問題との相違点等はありますか?」
A(伊達先生)「日本でも侍は髷を切ったことがあった。日本の場合は西洋の文明に対して遅れたものとして禁止された。辮髪のような身体に施しをするものや服装の一部が遅れたものと表象されて近代のスタンダードに合わせるようにという力学が働いているという流れはだから似ている話である。人間に関係するような「装う」というのは違う文化同士の出会いや力関係の中でも影響するようなものになっている」
付け加えて、伊達先生は日本の中高の制服問題もヴェール問題と似ているんじゃないかという指摘が一部あるとも指摘されており、天然パーマの生徒に対してストレートパーマを当てさせられることもあり、議論になっているということもお話しされていた。
Q(学生)「ヴェールは元々は安全を確保するような意味であり、相続権を認めることも当初は進歩だったわけですが、宗教は時代が進んだ中で権利などが平等にするようにするにはどのようにすればいいでしょうか?」
A(伊達先生)「相続権などクルアーンのできた時代にとっては進歩的なものの、言葉として残ってしまい絶対的なものや新しい守るべき規則になってしまうことがある。これは神学においては良くあることだが、その教えの精神に立ち返って考えるという人もいる。これは宗教についてよくあることだが、この解釈は大事なものであり多くの人が議論をしている。一方で保守派からは反発を招くこともよくある」
Q(学生)「ヴェールというテーマから「装い」に関連して、中国で昔は一度着ないようになったような服というのがあったりするが、ブームがあってまた着るようになるということがありました。ヴェールはそういった文化のようになるのでしょうか?」
A(伊達先生)「ヨーロッパでは民族で伝統的な服を着るようなものは好意的に見られることもありうる。パーティのような席で中国のそういった伝統的な服装が好意的に見られる可能性が高いのではないか。ただし、文脈によって民族衣装というものはポジティブかネガティブか難しいという面があるため、装う戦略を考える上では考慮する必要がある。
ヴェール問題について考えると、怪しげな意味合いもあったのかもしれない。エキゾチックな意味合いでのポジティブさはあってもそこまでよく見られることはなかったと思う。その上で、アラブ社会主義の影響が強かった20世紀なかばまで西洋的な近代化は進む一方で、西洋的な近代化の限界や近代化の別の方向が出てきた時に、再ヴェール化するようになって歴史を遡ったようになっている。この再ヴェール化は以前のヴェールとは異なる意味合いを持たせようとしていると考えることもできる。女性の男性に対する服従の意味合いを持っているように見えるけど他にもさまざまな意味合いがあるように思う。さまざまな意味合いがあると考えられる。」
Q(学生)「ヴェール論争についてお話しされたが、伝統的な風習に対して議論が起きている例として中国には結婚の時、男性が女性に結納金を納めるという問題があります。これを守ろうとする意見もあれば反対する人もおり社会問題となっています。こういった問題がある時にどういうことを考えればいいかお聞かせください」
A(伊達先生)「日本でも同じような問題がある。例えば葬式の簡略化などが挙げられる。こういった潮流は今のライフスタイルに合っている場合もあれば集まった方がいいこともある。中国の飲食店ではスマホで注文できるが日本では店員を呼んで注文した方がいいと思うことがあるが、外国人として中国のお店に訪れるとスマホで注文できる方が楽なこともある。このように両方の面があると思うが、グローバル化社会で経済の論理が強いかもしれないがなくなってしまうもの、昔からあったはずのものがどこも似たようなものになるのはなるべくない方がいいのではないか。ただ、新しい技術があることでローカルなところにもチャンスがあるということなのでそこで何が行われていくかが大事なのかなと思う。ヴェール問題に関していえば昔とは変わっているところというのもあり、例えばヴェールを被っているという状況でも意味合いが変わっているということもある。同じように見えても前とそのまま同じというのはありえないことで変化を見て分析すること大事である」
質問が尽きない中、授業は終わりを迎えた。授業の結びに先生も述べられていたが、関係された先生方、またとりわけ通訳を務められた肖慧文さんと唐懿昕さんの両氏の多大な尽力のもと授業は行われた。両氏はほぼリアルタイムで日本語でも複雑な講義内容を通訳した上で、質問に対する対応やリアクションペーパーの翻訳、授業のレジュメの準備などさまざまな場面で活躍されていた。円滑な授業の背景には両氏が事前に先生の授業音声や論文に目を通し、万全な準備が不可欠であっただろう。授業時間以外には、参考文献の中国語訳と日本語訳の違いについて先生と知見を共有する姿も見られた。
(写真:伊達先生、通訳を務めた肖慧文さんと唐懿昕さんが授業前に打ち合わせをする様子)
南京を実際に訪れ授業を行った伊達先生の様子はもちろんのこと、多大な貢献をした関係者の活躍を記録として残した上で講義録の結びとしたい。
通訳:南京大学日本語学科M2肖慧文・唐懿昕
(文責:大西)
コメントする
- 他の授業をみる



