ディシプリン(学問領域)に
とらわれない思考を身につけたい
第7回 03月20日 猿渡 敏郎
まとわず魅せる魚の装い
魚類は多様性に富み、脊椎動物の半数を占めます。渓流から深海まで出現し、生態も様々です。さらに、魚は人類にとって貴重な動物性蛋白源です。そんな魚が、弱肉強食の自然界で生き抜き次世代を残すために、どのような工夫をしているのでしょうか?!何もまとわない魚が、命と一生をかけて何をどのように「装い」生きているのか?魚と人とのかかわりを、研究する意義も含めて紹介します。
- 講師紹介
-
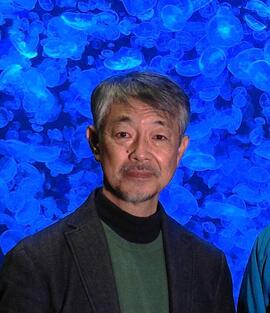
- 猿渡 敏郎
- 東京大学大気海洋研究所 助教。研究のキーワードは、「喰える雑魚の研究」。魚は水産資源という視点から、食べておいしい深海魚の「メヒカリ(標準和名 アオメエソ)」、海のロマンを掻き立てる「シーラカンス」、深海魚のスーパースター、「チョウチンアンコウ」など、魚を案内役に人を海へと誘う研究を色々としています。
- 授業風景
魚は非常に多様である。魚類は全世界で35700種が確認されているが、これは脊椎動物の半分の種が魚類であることを意味する。毒を持たないフグもいる。
チョウチンアンコウだけでも166種類が存在する。深海魚の多くは発光器を持っている。光の届かない深海でなぜ発光器?と思うかもしれない。しかし、実は深海にも光は届いていて、魚は腹部にある発行器から光を放つことで、自分の影を隠しているのだ。
また、先生は8匹のオス個体がメスに寄生するチョウチンアンコウを発見し、その個体の大きさを記録した。生殖における非常にレアなケースであり、先生自身もその大発見にびっくり仰天したようである。
実は新種が見つかる過程というのも非常に面白いものだ。といっても、「新種が見つかる」という表現は間違っているかもしれない。というのも、海のなかにその魚はすでに存在しているからだ。どちらかというと、人が、もっというと科学者がその魚を新種と認定することによって、はじめて魚は新種と記載される。
最近は、DNA解析の進展により、従来は形態学的に見た目からは区別できなかった個体が、実は別個の種であることが確認されたり、あるいは全く見た目の異なる魚が実は同じ種の親と子であることが判明したりしている。
日本の食卓に並ぶサンマが初めて新種として記載されたのは、なんと黒船来航のときである。ペリーは、その事業と並行して、海岸を測量したり、日本近海の魚を採集したり、様々な事業を好き放題やっている。実は、新種を分類するといった植物学・海洋生物学の歴史も西洋の植民地主義と決して無縁ではないのだ。そのような学問を帝国科学という。博物館、美術館、植物園、動物園、水族館、熱帯魚といった物を展示するという営みも、帝国主義的な歴史と深いつながりがあることを忘れてはならない。
人間にとって、特に日本人にとって魚は日常的に食される非常に身近な存在と言えよう。しかし、魚の一生、どこで生まれ、どのように成長し、というものは実は明らかにされていないものがほとんどである。世界に存在する35700種の魚のうち、子どもの頃の状態、仔稚魚の状態が判明しているのはわずか2200種に過ぎない。ちなみに、日本においては、国内の4748種の魚類のうちなんと1500種は仔稚魚の形態が判明している。日本の稚魚分類学は比較的発展していると言えるだろう。
実は、魚の一生・魚の生活史を明らかにすることは、魚の資源を管理するうえで非常に大事な観点である。魚というのは、自身で繁殖するためとても持続的な資源とも思えるが、その一生のサイクルが分かっていないようでは、人間が魚資源を利用するうえで支障がある。水産学の永遠の課題だろう。
さて、先生が研究にとりわけ力を注いできたものの一つにシラウオがある。川と海を往復する遡河回遊魚だと思われていたが、涸沼という汽水湖で猿渡先生が調査を行って、出現状況をまとめたところ、全生活史を涸沼水系内で完結する汽水魚であることが判明した。のちに似たような全国の他の水域でも同様の結果が得られた。先生の成果の一つである。
また、先生がとりわけ心血を注いで研究してきたもののなかに、深海魚のメヒカリ(標準和名:アオメエソ)がある。この魚、非常においしいそうだ。もともとはこの魚の取れる深海周辺の漁港で食べられてきたが、おいしいとの評判が徐々に津々浦々へと広がり、現在では全国で食べられる魚となっている。なんとこの魚、耳石の輪紋から日令、生まれてきてからの日数を知ることができる。一日生きる毎に輪紋が増えるのだ。メヒカリは、稚魚は海の表層、成魚は海底を生きるが、いつ個体が表層から海底へ移動したかを知ることもできる。それは、着底輪というものがあり、輪紋の幅が変わるためである。個体をひとつひとつ解析することによって、メヒカリの生まれてくる場所、さらに個体がどのように移動しているのかをおおよそ推定することができる。
魚の魅力は何といっても、横方向の地理的な移動だけでなく、縦方向、すなわち海の表層から深海までの移動があるということであろう。魚はときにとてもダイナミックな三次元的な移動をし、これは陸上を生きる私たちとは大きく異なる。
そして、授業では他にもシーラカンスやアユを始めとして、様々な魚を紹介いただいた。どれもユニークな研究や歴史がある。
また、実際に魚をどのように調査しているかも興味深い。調査船に何日も乗り込んで、採集した個体をひとつひとつ分析するプロセスは、非常に根気のいる、泥臭い作業である。その様子を軽妙な口調で猿渡先生には紹介していただいた。
猿渡先生は、高校生に実際に深海魚を触ってもらい、食べてもらうような活動もしている。魚についてより深く知ってほしいとのことだ。そして関連分野の大学へ進学することを願っている。
中国で食べられている魚は、日本のものとは異なることも多い。授業で身近な例として挙げられていたサンマやアユは、多くの中国の学生にとって決して身近なものではなかっただろう。しかし一方で、フグを食べる地域出身の学生もおり、共通の食文化というものも見られたのは非常に興味深かった。
そして中国の食文化は非常に多様であるが、中国滞在中も、さまざまな種類の魚類を喰らい、スーパーマーケットや市場でそのような魚が売られているかを見学した。
授業の終わりに、先生の研究室の資料を我先にと見に来ていた中国の学生が印象的だった。中国の学生にとっても、魚という話題は、非常に面白いものだったに違いない。
授業中も多様な観点からの質問があった。環境の変化による魚の装いの変化に関する質問に対しては、もともと南でしか見られないものだった魚が、北の方でも見られるようになったとの説明があった。また、なぜ光の届かないはずの深海にいる魚が鮮やかな赤色をまとっているのかという質問があった。それに対する返答としては、実は深海にも光は届いているのだということと、そしてその届いている光が地上と比べて赤色に偏っていることが挙げられた。深海の魚の多くが真紅なのは深海で目立たないようにするためであり、地上で赤色に見える魚は深海では黒く見えるのだ。
魚は丸裸で服をまとっていない。ありのままの姿で泳いでいる。
しかし、魚が私たち人間に見せるその姿は様々である。百魚繚乱である。
そんな魚の魅力が、少しでも読者のみなさんに伝わっていれば嬉しい限りである。更に興味のある方は、猿渡先生の研究成果をぜひご覧いただきたい。
通訳:南京大学日本語学科M1彭愛楽・劉逸舒
(文責:丸山)
コメントする
- 他の授業をみる