長谷川 寿一
ヒトとチンパンジーのあいだ ――ヒトはどのように特別な類人猿か――

ヒトは遺伝学的近縁性からみれば、チンパンジーと最も近く、チンパンジーからみても最近縁種は、ゴリラではなくヒトである。ヒト・チンパンジーグ ループは、他の類人猿にはみられない特徴として、雄同士の強い絆や集団狩猟を共有している。しかし他方、ヒトは、チンパンジーや他の類人猿とは明白に異な る認知能力を発達させた。とくに社会認知に関連した、模倣、共感、教示、他者の内面理解(マインドリーディング)、言語コミュニケーションといった能力 は、ヒトという種に特異的な能力であり、これらの認知能力のおかげで、ヒトは文化を切り開き、文明を築き上げた。では、そもそもなぜ、ヒトはこのような特 殊な能力を進化させたのだろうか。
霊長類における脳の進化を説明する仮説としては、群れ生活における社会関係の認知と他者操作が強い選択圧として働いたとする社会脳仮説が主流であ り、群れサイズと新皮質の相対サイズの強い相関が報告されている。しかし近年の論文では、繁殖開始年齢と体サイズの影響を除去した脳容量の間により強い相 関関係があることも指摘されている。ヒトは、火を用いた調理と肉食によって、類人猿の伝統である果実依存性から解放され、集団生活を安定化できた。加え て、子の養育に父親や祖母などが積極的に関わり、手間暇のかかる子育てを協同で行なうようになった。結果、繁殖開始年齢が遅い大きな脳を持つ子どもを、他 の類人猿よりもはるかに短い出産間隔で産出できる。前述の人間固有の社会的認知能力は、この協同繁殖のための適応ツールとして進化したのだろう。
[講演者紹介]

1952年生。神奈川県出身。1974年、東京大学文学部心理学科卒。1984年、同大学院人文社会学研究科心理学専攻博士課程修了。文学博士。国際協力 事業団派遣専門家、東京大学教養学部助手、帝京大学文学部助教授を経て、1991年より東京大学教養学部助教授、1999年より同大学院総合文化研究科教 授。2011年より同研究科長・教養学部長。日本学術会議第21期会員。専門は、動物行動学、進化心理学。
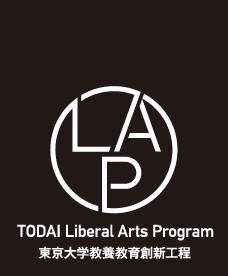
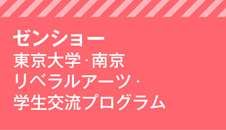
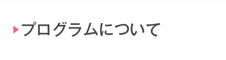

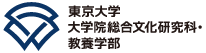
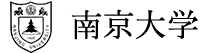


コメントする