山影 進
アジア地域制度構築とASEANの役割変化
2011年3月21日 15時~
ア ジアあるいはアジア太平洋の地域制度の多くが、程度の差こそあれASEAN(東南アジア諸国連合)という弱小国連合の存在に依存してきたことは繰り返すま でもないであろう。そして、これら地域制度の運営方針が、長年ASEANによって標榜されてきた原則(いわゆるASEANウェイ)を採用していることも多 かった。そうなった理由は、要するに、ASEANを含む広域の制度がASEAN域外国にとって何らかの意味で有用であったこと、そして域外国が広域制度に ASEANを取り込むためにはASEAN諸国の主張する運営方針を採用せざるを得なかったことによる。
しかしながら、アジアあるいはアジア 太平洋における地域制度は、きわめて複雑に入り組むようになった。とくに、今世紀に入ってから顕著である。そうした動きの中で、ASEAN自身が変容と変 質を遂げるとともに、ASEANとは無関係の地域制度が形成されるようになった。そこで、アジアあるいはアジア太平洋における脱「ASEAN依存」の地域 制度化と呼べる現象の進行を指摘することを本報告の目的とし、可能ならば、その特徴を探ってみたい。
報告では、ASEANを中心とする地域 制度の発達を確認した上で、新しい兆候である(1)域外諸国に見られる脱「ASEAN依存」の制度構築、(2)ASEAN諸国に見られる脱「ASEAN依 存」の指向性の2点を指摘する。引き続いて、地域制度の脱「ASEANウェイ」ないし脱「アジアン・ウェイ」をめぐる攻防についても整理したい。
なお、本報告は、日本のアジア政経学会2010年度全国大会(2010年10月23−24日、東大駒場)の共通論題<アジア地域制度の再検討:「アジアン・ウェイ」の動向と分析>における「アジアにおける脱「ASEAN依存」の進行——若干の観察から」が元になっている。
[講演者紹介]

1972年東京大学教養学部国際関係論分科卒業、1974年同大学院社会科学研究科修士課程修了。1974~1976年マサチューセッツ工科大学留学、京都大学東南アジア研究センターをへて、1980年東大教養学部助教授、82年マサチューセッツ工科大学より博士号取得。1991年東京大学大学院総合文化研究科教授。
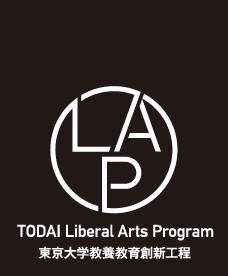
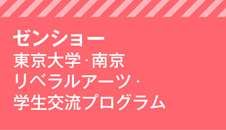
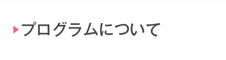

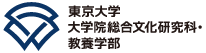
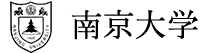


コメントする