崔洋一
日本映画の過去・現在・未来 映画監督の視線
『月はどっちに出ている』、『豚の報い』、『刑務所の中』、『血と骨』などで知られる映画監督の崔洋一先生をお招きしての南京大学での講演です。
[講演者紹介]

1949年長野県生まれ。1983年にベネチア国際映画祭に出品された『十階のモスキート』で劇場映画監督デビューを飾る。1993年、『月はどっちに出ている』で映画賞を多数受賞し、脚光を浴びる。1999年には『豚の報い』を手がける。2002年、『刑務所の中』でブルーリボン賞を受賞-。2004年には、『クイール』、『血と骨』を発表し、高い評価を得ている。
授業風景
3月16日午後4時より、南京大学外語学院(仙林キャンパス)にて崔洋一監督の特別講演が開催された。テーマは「日本映画の過去・現在・未来 映画監督の視線(从导演的角度观看日本电影的过去,现在和未来)」で、大島渚の作品「日本映画の百年」(1995年)を下敷きに、日本映画の過去、現在、未来を語るという内容であった。逐語通訳は刈間文俊先生が担当され、講演前半ではまず「日本映画の百年」を観賞した。
鑑賞後、崔監督は大島の描いた日本映画の百年が、大きく戦前、戦後復興期の映画会社による映画製作期、1960年代末以降の会社ではなく個人による映画製作期の3つに時期区分されていることを示した上で、大島が客観性を求めたオーソドックスな映画史を描こうとしつつも、そこには戦争を経験した大島少年の視線が色濃く反映されていると指摘した。監督によれば、それは科学技術や工業化による文明の進歩が人類に幸福をもたらすという予定調和的な世界観は幻想に過ぎないとするものであった。また、大島は一貫して日本人の「被害者意識」を批判していた。なぜなら、〈被害者〉とされる大衆は、時に、容易に〈加害者〉へと転化するからである。この批判性も、大島による日本映画史の基底をなしていた。他方、日本映画には、批判性のみならず大衆の精神的糧となる側面もあった。ただし精神的糧として映画が機能するということは、作り手と観客が一致することを意味する。それはすなわち、作り手と観客の葛藤の不在を意味していた。戦前の、政府や軍による抑圧を経験してきた作り手は、映画を通して〈日本〉、あるいは〈日本人〉の歴史性を掘り下げていった一方、そこには〈普遍性〉が欠如していたのであった。
戦後復興期から1980年代までの経済成長期は、映画にとっては衰退期であった。それはすなわち、映画が大衆の精神的糧となる役割を手放していく過程であった。日本で映画の観客が最多であったのは1950年前後であり、大島渚がデビューしたのが1959年であった。大島が映画人として活動を始めたのは、映画会社時代が終焉し、予定調和的世界観=幻想が終焉し、テレビが出現した頃であった。そして1960年代末には個人製作の時代が到来するのであるが、それはなぜ到来したのか。それは監督によれば、社会が多くの矛盾を孕み、人々、とりわけ若者が苦悩するとき、それを代弁する者が現れるからである。そしてそのような、時代に切り込む映画は、マニフェストの有無に関わらず、その映画そのものがマニフェストとなるのであった。そこに共通するのは、様々な作家が、様々な感情を、自己を通じて表現する、という作家精神の多様性である。
だが、このような作家性の強い、作家の主張を映画化するような映画は1980年代には終焉を迎えた。そして〈日本〉、〈日本人〉の歴史性を追求から、国境を越えた映画へと方向を転換してゆく。例えば北野武の映画は日本では必ずしも興行的に成功しているとは言えないものの、世界的にその世界観が評価されており、その意味で北野の映画は世界性を獲得していると言える。また宮﨑駿に代表されるようなアニメーション作品も同様であろう。このような〈普遍性〉の追求が現在の映画界の流れを作りだしている。中華圏においても、1980年代以降の王家衛、近年の刁亦男、王兵等の作品がその潮流に位置するものとして挙げられる。
現在、まちの映画館が既に衰退し、シネマ・コンプレックスが席巻するのみならず、インターネットやストリーミングが映画館以上の観客を獲得する状況にある。だとしても、スクリーンと観客により成立する〈映画〉を支持し、〈映画〉において「場」を共有することの重要性を改めて監督は主張した。
質疑応答では、大島渚に対する評価や大島からの影響について、また〈映画〉の衰退に対してどのように向き合うかなど、活発な議論がなされた。
(文責:東京大学 新田龍希)
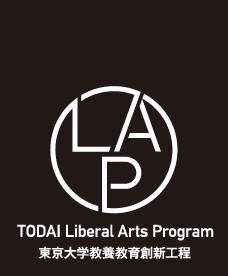
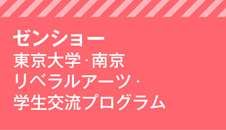
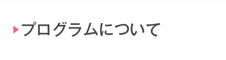

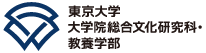
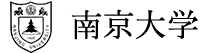




コメントする