小森陽一
夏目漱石『吾輩は猫である』の猫の毛の色
[講演者紹介]

1953年、東京生まれ。東京大学大学院教授(日本近代文学)、夏目漱石研究の第一人者。「九条の会」事務局長。著作に、『文体としての物語』(筑摩書房 1988年)『構造としての語り』(新曜社 1988年)、『座談会 昭和文学史』(共著、全六巻 2004年完結、集英社)、『天皇の玉音放送』(2008年、朝日文庫)、『漱石を読みなおす』(1995年、筑摩新書)、『死者の声、生者の言葉 文学で問う原発の日本』(2014年、新日本出版社)など多数。
授業風景
南京大学特設講演のレポートを掲載いたします。
南京大学特設講演
『吾輩は猫である』の猫の毛の色
小森陽一
3月15日午後4時より、南京大学仙林キャンパスにて日本近現代文学が専門の小森陽一先生の特別講演が行われた。講演タイトルは、「『吾輩は猫である』の猫の毛の色」。夏目漱石没後100年の本年において、漱石の最初の小説である『吾輩は猫である』をポストコロニアル批評の視座から読み直す実践であった。小森先生は、まず、『吾輩は猫である』連載第1回の冒頭「吾輩は猫である。名前はまだない。」から、「名前はまだつけて呉れないが欲をいつても際限がないから矢張此教師の家で無名の猫で終る積りだ」という第1回の末尾の2箇所に注目し、『吾輩は猫である』において「無名性」が小説構造の要に位置付けられていると指摘する。
他の猫たちは、「軍人の家」で飼われている「白君」、「代言の主人を持つて居る」「三毛君」、「車屋」の「黒」など、飼い主である人間たちによって、「個別性」や「単独性」を捨象された「毛」の「色」に還元されているというのだ。一方、「吾輩」とその飼い主苦沙弥先生はこのような「安易な関係性」を拒絶している。小森先生は、当時の歴史的な背景について言及しながら、「軍人」「代言」「車屋」「書生」といった飼い主の職業は、明治維新以後の文明開化・富国強兵政策の中で新たにつくり出された職業にほかならないと指摘する。
それだけではなく、猫の「吾輩」は、エリート知識人の予備軍である「書生」のことを、「人間中で一番獰悪な種族」という「人種主義的な語彙」で表す。『人種不平等論』(1853年~1855年)において、フランスの東洋学者ゴビノーは、「純粋民族」としての「アーリア民族(なかでもゲルマン民族)」の優位性を主張し、皮膚の色による「種族」の優劣が、科学的装いをこらしながら、人種主義的な言説として主張した。そうした言説に照らし合わせると、猫族の毛の色は、人間でいえば「皮膚」の色にあたる。小森先生は、ポストコロニアル批評の実践として、毛、すなわち「皮膚」の色で飼い猫に名前をつける「主人」と「猫」との関係に、「新大陸」発見後の大西洋奴隷貿易における「主人」と「奴隷」の関係の四百年近い歴史を読み込んだ。
また、「胃弱」の「主人」として描かれている苦沙弥先生の「皮膚の色」は「淡黄色」と表現されている。そのため、「胃弱」であるために胃薬である「タカチヤスターゼ」を飲んでいることが描かれている。この「タカチヤスターゼ」という言葉からは、日露戦争における旅順攻略戦の激戦報道との接点が見いだせる。「吾輩は猫である」の第一回を読んでいる読者は、1894年に日本の化学者の高峰譲吉が麹菌から消化酵素「シアスターゼ」を抽出し、それに自分の名前の「高」をつけて、商品化した胃薬「タカチヤスターゼ」を想起せざるをえず、その新しく発見された消化剤は、戦時ナショナリズム下にある日本人にとってその象徴のひとつとして捉えられていたのである。
それだけではなく、苦沙弥先生の「淡黄色」の「皮膚の色」は、「黄禍論」、「イエロー・ペリル」(yellow peril)の記憶を呼び起こす。日清戦争の最終段階に入りつつあった1895年、ドイツの皇帝ウィルヘルム二世は、日本の勝利を黄色人種の興隆と呼び、「ヨーロッパのキリスト教文明にとって「黄禍」となるから、ヨーロッパ列強は力を合わせて対抗すべきだ」と主張した。つまり、「黄色」い「皮膚」を持つ黄色人種を敵視し、ヨーロッパ列強の中国への進出と分割支配を正当化する議論が「黄禍論」であった。『吾輩は猫である』という小説には、この記憶が焼き付いている。

それに加えて、『吾輩は猫である』の中に現れる日付、一九〇四年の十二月一日と四日、その翌月の五日は、旅順攻囲戦において、最も激戦となった「二〇三高地」をめぐる戦闘の記憶を想起させる。乃木希典が指揮する第三軍は旅順正面攻撃に失敗し、その後、高さが203メートルあったため、「二〇三高地」と呼ばれた高台を一一月二六日から攻撃した。日本軍は、5000人以上の戦死者と、1万人以上の犠牲者を出した激戦であった。その「二〇三高地」を占領したのが一二月五日なのだ。その頃の新聞報道は、「二〇三高地」戦報道一色であった。しかし、苦沙弥先生は、友人の「金縁眼鏡の美学者」と、無名の画家・アンドレア・デル・サルトについて話しており、この二人は、「大日本帝国臣民の平均的な関心のあり方」や戦時ナショナリズムからは逸脱しているように設定されている。そして、ローマに出ることなく、それまでに確立された油絵の技法を次の世代に受け継ぐ役割を担ったアンドレア・デル・サルトは、肌の「色」の違いだけを口実に、同じ人間を商品化し売り買いし、生殺与奪の権を握って来た、「白」い肌を持つキリスト教文化圏のあり方を批判する無名な固有名なのだという。小森先生は、『吾輩は猫である』の中に、虚と実の世界両方をつなぐ「色」を表す言葉を見出し、ヨーロッパキリスト教文化圏の植民地主義の全歴史を読み直す実践を行った。(文・岩川ありさ)
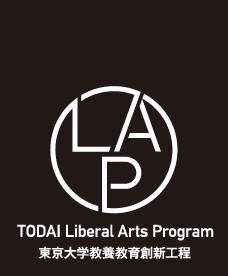
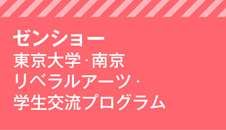
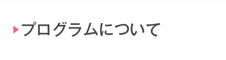

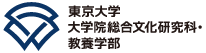
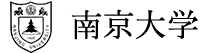



コメントする