ディシプリン(学問領域)に
とらわれない思考を身につけたい
第6回 11月14日 清水 晶子
変わるもの、変えられないもの、変わってしまうもの
固定的なアイデンティティや主体への批判をその出発点において取り入れたクィア理論は、そのため、しばしば可塑性や流動性に注目する議論として理解されて きました。とりわけ、セクシュアリティの流動性や創造的なジェンダー・パフォーマンスへの着目は、クィア理論のいわば「華やかで楽しそうな」魅力であったと言っても良いでしょう。けれども同時に、病によって「変容」を余儀なくされる身体や、あるいは「変容」のままならなさといったテーマもまた、クィア理論 にはその最初からつきまとっています。本講義ではクィア理論が「変容」をめぐるこの2つの側面をいかに扱ってきたのかを説明しながら、「わたし」や「わたしの身体」が「変容する」とはどういう事なのかを、考えていきたいと思います。
- 講師紹介
-

- 清水 晶子
- 東京大学大学院情報学環/総合文化研究科准教授。 英文学修士(東京大学)、MA in Sexual Politics、 PhD in Critical and Cultural Theory (University of Wales, Cardiff)。主な研究分野はフェミニズム/クィア理論。著書にLying Bodies: Survival and Subversion in the Field of Vision(Peter Lang Pub Inc, 2008)。
コメント(最新2件 / 4)
- 2012年11月18日 12:14 reply
ネオリベラルと呼ばれる思想について考えさせられることが多かったです。というのも、今は多文化主義を受け入れるのが当然とされ、そうすることが推奨されています。人種も文化も違うというだけで否定するのではなく、相互理解するべきなのだという考え方です。しかし、中にはどうしても硬直的になってしまう人たちもいるのです。保守的な人たちはそういった多文化主義にはついていけないと思う人も多いようです。そして、実は本当の問題は多文化主義という一見穏健な考え方が、その主義に反する人々を排斥しようとする偏った考えなのではないかということなのです。レズビアンの人々にしたってそうです。異性愛社会に受け入れられるためには、受け入れられやすい形にならなくてはいけない。あるいは、異性愛社会が自分たちの基準で決めた「レズビアンはかくあるべし。共存はできるが、その形であるべし」というものに順応しなくてはしなくてはならないのです。もしそれ以外の形でレズビアンが存在するなら、彼女らはレズビアンですらないとみなされ、レズビアンの異端とみなされることになるのです。そこにあるのはただ排除の観念です。もっとたちが悪いことに、異性愛者会側は寛容に受け入れてやっているつもりなのです。実のところ、偽の寛容性の裏側にはただの依怙地が潜んでいることはあきらかです。ではいったいどのような主義が正しいのか。そもそも、ある種類の人間をこんな風だというふうに決めた段階で、それ以外の人々をカテゴリーに入れられない異常なものとしてみなくてはならなくなるのです。私は定義が存在しない世の中が来るべきだと思います。あるいは、定義は速やかに更新されねばならない。そうでなくてはならないと思いました。
- 2012年11月20日 22:23 reply
充実した講義、誠にありがとうございました。大変勉強になりました。
我々が生きる現代は昔と違って多文化主義が多く受け入れられている良い時代だ、と思いこんでいましたが、私には何も見えていなかったようです。
クィアが「排除」される時代から、クィアが異性愛者・マジョリティに危害を与えないものとして「消費」される時代へ。構図としてはさらにグロテスクになったように感じます。さらに、クィアは自らが生きやすいように、異性愛者に受け入れられる形に「変容」することを選ぶ。この変容に失敗した場合には、協力体制からやはり「排除」される。クィアが大人しいものとして飼いならされてしまったように見えます。
過去のものとなってしまった感のあるラディカルだったころのクィア理論の見るべきところを再確認する必要性を感じさせられました。
- 2012年11月20日 22:27 reply
2回にわたる講義、どうもありがとうございました。前回のコメントでも書いたように、クィア理論を始めとする現代のセクシュアリティやジェンダー・パフォーマンスを巡る議論は私にとって新しく、故に本講義内容を完璧には理解できなかったのですが、非常に興味深く面白いものでした。
今回の内容とは少し的が外れるのですが、新しい枠組み(枠組みというよりも捉え方といいますか)が創成されている動きを学ぶと、既存の「そのもの」の本質とは何か、という問題を意識せざるを得ません。変わることのない身体的真実に基づいているにも関わらず、昨今のジェンダーは変容可能性を持つ、或いは身体に従属しないジェンダーなどを考えるとつくづく実感します。捉え方で本質が変わるのか。或いはジェンダーというものは本質(実態)などなく、それを取り囲む環境(理論)によって常に変容する不定形のものなのか。しかし一方でクィアムーブメントの流れから、不安定であった/であることを強制されていたマイノリティが自己を主張し安定の方向性に向かっている実情を考えると、根幹は決まっていてそれが靄に隠れてしまっているが故に社会から浮いてしまっているのではとも思います。
以上のような思索は直接的には今回の講義で学んだことと関連しないかもしれませんが、この理論を深めることでさらに先に進めるのではと思いました。
コメントする
- 他の授業をみる
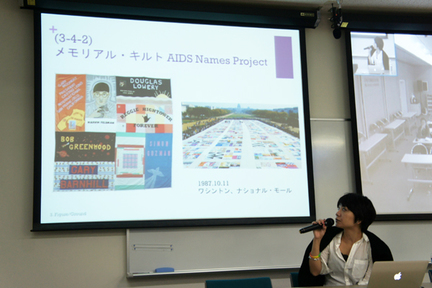


本当に充実したご講義をしていただきありがとうございました。クィア理論の可能性と限界、これはジェンダーだけでなく変容という事象一般に敷衍して述べることのできる考察だったと思います。capableな「わたし」の広がりがそうではない「わたし」を排除することになるというのは、マイノリティに対する現代社会の表層的理解を強く示唆する指摘です。本来マジョリティが妥協をするという発想自体が差別的視点を持っているというのに、マイノリティが妥協をして同化しようとする現在の流れは非常に空しさを覚えます。同化や差異の主張という考え方が初めから存在しない世界こそがあるべき世界だと思いますが、そのためには多くの人が今日の授業の内容を理解し、より高次の中立性を持たなければなりません。大学内を見ただけでも教授のお話を聞いた人間よりも聞いていない人間の方が圧倒的多数であるという事実は、講義の素晴らしさ故に悲しいものに思われました。